2022年12月25日
クリスマスなのに、令和4年分確定申告の準備をしています。

会計ソフトに1年分の領収書データを入力
世間はクリスマス。
家族や友人、恋人と楽しく過ごす日。
私のクリスマスは、子供にワンピースカードとポケモンのグッズを渡して終了。
その後に私は事務所で会計ソフトを操作しています。
ファイルに溜まっていた1年分のレシートを一気に入力していました。
ちなみに私は「わくわく財務会計6」という会計ソフトを使用しています。
理由は買い切りでリーズナブルな価格だからです。
サブスクの方が便利かと思いますが…
年単位で使用すると、かなり割高になってしまいます。
クリアブックに一月ごとに領収書を分類していたので、作業自体は2時間程度で終了。
今年度の決算がほぼほぼ確定しました。
今年の2月から5月あたりの出費がエグイことになっていました。
領収書やカードの支払い明細を見ながら…
何でこんなものを買ってしまったのだ!
購入した当初は、投資と言い聞かせて購入した物の数々。
必要になると思い買ったけど、殆ど読んでいない専門書の数々。
新しい業務の柱を作るべく参加したセミナー。
ウン万円の数字が掛かれた領収書を見てため息が…
さらに会計ソフトに計上された数字を見て…
この調子で無駄遣いをすると、マジでヤバいと思い後半は緊縮財政。
あとは御用納めの日に、記帳して最終的な数字を確定。
ラストはイータックスで、数字を放り込んで確定申告終了。
税務署のHPを見ると、令和4年分の確定申告は2月からとなっています。
弊所は毎年正月休みか正月明けに申告を済ましてしまいます。

私のモットーは、嫌な事はいの一番に片付けるです。
嫌な事を後回しにすると、心の片隅で嫌な思い引きずります。
兎に角、自分に手元にボールを抱え込みたくない。
事務所の仕事、プライベートでも飛んで来たら即座に投げ返します。
年賀状も12月20日前後に投函も済んでいます。
話を戻して、国税電子申告・納税システム(e-Tax)だと、何故か正月明けでも確定申告ができます。
電子申請は慣れると楽ですね。
同じ電子申請でも建設業許可は中途半端でやり難い。
その内、産廃収集も電子申請になるのでしょうかね。
電子申請になるとは一向に聞きませんが。

取りあえず、今年も何とか事務所を維持できました。
来年も必死に頑張って行きたいと思います。
多分何とかなるでしょう。
ケセラセラってヤツです。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at
10:54
│Comments(0)
2022年12月18日
大先輩が言っていた値引きと相みつ客は止めとけは正しかった

今日は行政書士の相見積もりと値引きについて。
多くの行政書士は、値引きや相みつはダメだと言います。
これを見て、自社と業界を守るための方便と思うかと。
実際に理由なき値引きや相見積もりで仕事を取るのはリスキーですね。
ネットスラングで時折見かける
謎の勢力「値引きと相見積もりの業務受注は止めとけ!」
俺「うるせぇ!、」
暫くしてから…
俺「値引きと相見積もりの業務受注は止めとけ!」
多くの場合でこの様な感じになりますね。
私も開業当初は、上記のやり取りを行っています。
値引きと相見積もりは避けた方が良い理由を上げてみます。
・業界の価格破壊を推し進める
・貧乏暇なし事務所へ
・集客コストに大差なし
・値段が変わっても責任の重さは一緒
・価格と釣り合わないクオリティ
・常連になられると困る
業界の価格破壊や貧乏暇なしは言わずもがな。
単価を下げれば、件数を取る必要があります。
正直、相場を乖離した値段なのでモチベーションはだだ下がり。
常に時給を意識しながらの仕事になります。
(全然面白くない仕事になるかと。)
集客コストですが、値段で大きな差がつきません。
サイト集客するにせよ、リアル営業するにせよ。
1割りや2割引き程度では、強力な集客力は生まれません。
価格だけで勝負するなら、いわゆる業界最安値をさらに下回る価格にする必要が。
行政書士の業務は、究極的に言えば許可を取る事です。
それ以外の事は、おまけに過ぎません。
顧客は相場の半額だろうが、相場通りだろうが関係ありません。
報酬を支払うのだから、結果を出せと言われるだけです。
責任の重さは、高額でも激安でも一緒です。
行政書士側はリスクだけ重くて、リターンがない状況です。
顧客の大半は良い人ですが、ごく一部の人の話です。
相見積もりが好きな方は、いわゆる賢い消費者です。
値段と釣り合わない品質を求められる傾向が多いです。
その割に支払いは渋られる事も多いですね。
催促するも反応なしで、ストレスが溜まる結果に。
最後に常連になられると困るですね…
首尾よく業務完了したとします。
その後に更新などでリピートがあります。
(許認可はリピートが最大の旨み)
だけどもリピート時も激安価格です。
値上げなどさせてもらえません。
また激安で請負った顧客から紹介が来る可能性も。
紹介客も激安価格&キックバック。
渋い顧客が紹介をバンバン振ってくることは稀ですけども。
マジで言います。
値引きと相見積もりからの受注は止めとけです。
今日はここまで
Posted by ミスター・フー at
13:15
│Comments(0)
2022年12月17日
行政書士の休みは土日祝日が確実だと思う。
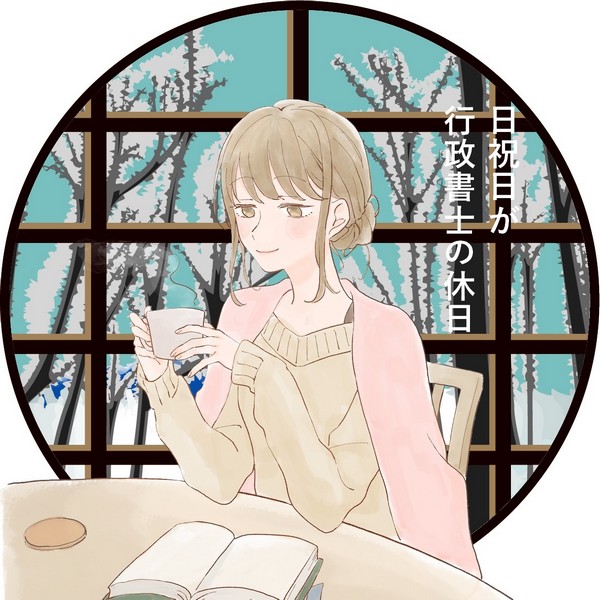
行政書士事務所の休日は日祝になりがちですね。
今日は行政書士の休日について。
大半の行政書士は自営業です。
一部、行政書士法人や個人事務所で勤務する人もいますが…
(全体から見ると極めて少数)
自営業のメリットは、休日を好きに決めることができます。
(開店休業で毎日が日曜日も…)
私も急ぎの仕事がない時は、昼寝やアマプラ動画を見ています。
(実務の勉強するなり、営業をしろと突っ込みが)
ただ毎日が日曜日は精神的に来ますね。
特に支払いが重なる月末に通帳残高を見ると。
徐々に減っていく預金残高が、ボディブローの様にジワリと効いてきます。
これについては自営業の通過儀礼です。
残高が減らない程度に仕事が来るまで耐えるしかないですね。
毎日が日曜日だと、休日のお問い合わせも嬉しいものですが。
(ただ経験上、営業時間外の電話は筋が良くない人が多い傾向あり)
それかアルバイトするかです。
大阪会は建築振興課の窓口業務があります。
我が支部の同業者も行ってる人は多いです。
建設業許可の完成書類を見る事が出来るのと、回りも行政書士であること。
また建設業許可に関われるので、行政書士っぽい仕事が出来るのが良いですね。
また収入もある程度入って来るので最高です。
それはともかく行政書士の休日は日祝に集約する話。
(これに親しみ過ぎると茹でガエルになるので注意)
話を戻します。
行政書士事務所は休日が日祝日になる件です。
理由はお客様が、休日だと思っているからです。
事前予約とかが無ければ、電話も鳴りませんしメールも来ません。
行政書士も客商売です。
休日もお客様の動きに合わせるのが確実ですね。
平日だとお客様や役所から、電話や連絡が普通に入ります。
いつ電話が掛かってくるかと身構えながらだと心が休まりません。
ゆえに許認可系の業務は土日祝日が休日に、
配偶者ビザや相続など個人系の仕事は日祝が休み易いです。
個人系の場合、土曜日に面談が入る事が多いです。
(会社員は平日に時間を作れないため)
自営業の建前上は、好きな日に休日を作れば良いです。
しかしながら平日を定休日にしても、お客様から連絡があれば対応することに。
また役所が開いている日を休みにするのは非効率的です。
あと家族が居る場合も土日祝日を休日にせざるを得ないです。
子供のイベントや家族サービスが難しくなる。
自営業に休日は無いと言われます。
個人的には、どんなに忙しくても週に1日は休む事をお勧めします。
行政書士事務所の経営は何十年と続きます。
ブームに乗って、開店して半年で閉める様な商売ではないです。
以前は小売店を経営していた時の頃を考えると。
確実に休日が取れるのはありがたい話です。
店をしている時は、100連勤、200連勤とか普通にありました。
そんなことをツラツラと考えたことを記事にしました。
ブログ記事は思いついた事を書けばよいのです。
今日はここまで
Posted by ミスター・フー at
12:17
│Comments(0)
2022年12月11日
メールの問い合わせは教えて君が非常に多い

今日は行政書士のレスポンスについて
結論を言うと、即レスは本当に本当に大切です。
特に私のようなネット集客主体の行政書士事務所だと。
建設業にせよ、在留資格にせよ。
お問い合わせは、ほぼ電話で来ます。
メールでも来ることはありますが…
聞きたいだけの人が殆どですね。
(電話だったら、面談になる可能性が高いから)
もっとも電話でも教えて君は一定数混ざりますけども。
行政書士の中には、メールフォームを取っ払っている人も居ます。
(メールの問合せが少ない、確度が低い内容しかこない)
逆に電話番号を公表しない事務所もありますね。
ベテランで新規の受付停止みたいな事務所とか。
単純に電話対応したくない事務所とか。
正直言って、毎日の様に掛かってくる営業電話には辟易しますけども。
それも着信拒否の蓄積で、多少は減らせるかなと思います。
個人的な感覚ですが…
依頼への確度が高い問い合わせは、その時に対応しないと取りこぼします。
何らかの事情で電話に出られなかった場合…
10分後に折り返しても時すでに遅しです。
他所の行政書士に電話して、対応した事務所に持って行かれます。
悲しいですけど、許認可やビザ申請は自分である必要はありません。
他所の事務所でも対応可能な商品です。
即レスが出来なくても受任できるのは、決め打ちのお客様くらいです。
どうしてもウチの事務所に、お願いしたいと思ってくれている奇特な方は少ないかなと。
最初の頃は、お客様からの電話が怖い、営業電話が鬱陶しい。
だけども慣れます。
今はチャットやLINE、Zoomなど様々なITツールがあります。
電話は時代遅れと言われますが。
お客様が電話やFaxなら、それに対応しなければいけません。
行政書士は実務家だけど、行政書士事務所はサービス業です。
もっともサービス業と言っても、虚偽申請や違法はダメですけども。
虚偽を強要する方は、お客様ではありません。
士業の仕事はコンプライアンスへのサポートです。
私は専門家でござい実務家です。
それで食べられるのは、一握りのトップ層だけです。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at
10:52
│Comments(0)
2022年12月03日
建設業許可電子申請セミナーを受講した

2022年11月28日の15時から日行連主催の建設業許可の電子申請セミナーに参加しました。
講師は国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課の担当官です。
短い時間ですが、大変有意義なセミナーだったと思います。
内容は電子申請の概要と操作方法の触りの説明。
講義が1時間なので深い部分までは難しいですね。
まず電子申請システムの名称は、JCIP(ジェイシップ)と言います。
英語表記の頭文字を取ったものです。
スタートは令和5年の1月10日(火)です。
国土交通省と42道県がこの日に始めます。
東京都は令和5年内に開始予定。
大阪府、兵庫県、京都府、福岡県は未定と…
大阪府で知事許可メインの弊所は、電子化は当面先の話ですが。
(早くても数年後の話になりそうな感じがします)
始まった時にバタつかないように勉強しておく必要があります。
全体的な感想は、使いこなせれば申請は楽になるかなと。
同時にうっかりミスで致命傷に至るリスクがあります。
特に会社の登記簿を取らなくても申請できます。
役員の重任登記などが抜けていても気付かないリスクも。
(行政書士的には、登記情報提供サービスで取得が必須)
期限ギリギリで重任登記漏れを発見したら…
更新を飛ばす可能性がありますね。
次に建設業許可の閲覧がPCで可能になるとか。
これが実現されれば、南港まで行って何時間も待って固いイスに座って転記する必要がなくなります。
問題は膨大な資料が電子化されるまでにどれ位の期間が掛かるかです。
(大阪の場合、数年先か永遠にやって来ない可能性も)
説明を聞いていて気になったのが、行政庁の審査前に手数料納付がある様な感じでした。
よくよく聞くと、行政庁(地方整備局など)のチェックが済んでから納付指示が出るとの事。
申請と同時に納付だったら…
取り下げ指示で再度の提出で手数料の二重払いを危惧しました。
流石にこれは無いと思うので安心しました。
(役所にクレームの押し寄せるリスクを回避した?)
最大の特徴はバックヤード連携です。
国税庁と法務局のシステムと連携して、納税証明書と全部事項証明書の取得が不要になると。
少し微妙なシステムです。
地方税や市役所、社会保険関連は繋がらないのが不便ですね。
取得に手間がかかる奴は今まで通りの運用になります。
また法務局と連携でも登記簿は可能みたいですけど、無いこと証明には言及無し。
(多分、登記されていない事の証明書はNGなんだと思います)
住基ネットや法務局のない事の証明は、個人のプライバシーに深く関わるので連携しないのかなと。
(システムからの情報漏洩が怖いというのもあるかも)
また税務署の連携は、イータックスから自動添付という形になります。
民間の許可申請システムと連携するようですね。
ワイズで入力した情報が、そのままJCIPに反映される形になります。
わざわざ打ち直す必要が無いのは助かります。
また初回に取り込んだデータを次回の申請でも出力される形です。
これも有難いです。
行政書士が代理申請する場合、クライアント様と行政書士側の両者でGビズIDのプライムアカウントが必要になります。
申請するには、個人事業主だと印鑑証明書が必要です。
IDが発行されるまでに、2週間から3週間かかります。
代理申請する方法も独特です。
建設会社の方が委任状をJCIPで作成して、行政書士が承認する形です。
紙で申請する時は委任状にハンコくださいと言うだけでしたが、ひと手間増える形です。
何気に助かったのは、入力したデータをPDFで確認できる事です。
入管のシステムの様に、チェックし辛い形だったら嫌だなと思っていました。
データを飛ばす前に、PDFで行政書士とお客様の双方でチェックすることができます。
あと気になったは、添付書類に容量制限があるのかですね。
在留資格の電子申請は、5メガが限界です。
それ以上になると窓口申請になります。
建設業許可の電子化で、行政書士業界も色々変わります。
行政書士事務所の全国展開による競争激化は確実でしょう。
ネット広告は小規模事務所では手が出せない程に高騰するのが見えます。
すでにリスティング広告のクリック単価は、数か月前の4倍から8倍に高騰しています。
環境の変化に対応できなければ、淘汰されるのは自明の理です。
取り残されないように頑張ります。
今日はここまで
Posted by ミスター・フー at
14:17
│Comments(0)

 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン







